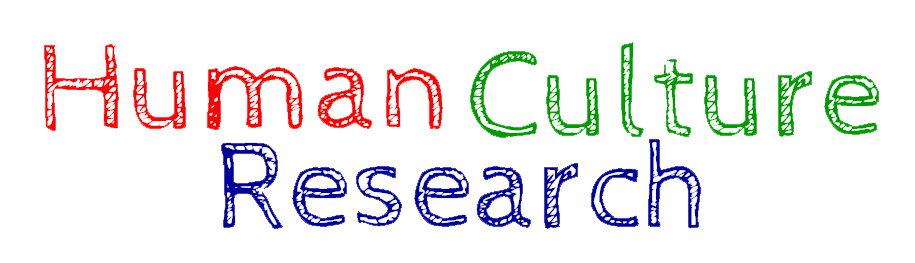食事の意味
食事は、食材を手に入れ、保存し、必要なら調理し、そして食べるという過程を含んでいる。かつてはこの全プロセスはヒトの身近にあったが、現代では、分業化により、最後の「食べる」という段階だけに関わるヒトが増えている。このように食事の過程が省略されていき、そして生存と意味のための儀式だったものが、多くの人にとって単なる消費行為になってしまった。全プロセスを含む食事から消費のみの食事への歴史的な変化は、いくつかの重要な変革を経て展開した。それぞれの変革を通じて、個人の関与という層は剥ぎ取られ、食事は抽象化されたシステムと産業に置き換わった。現代のヒトは自然と分断され、概念化した自己の抽象性の中に生物としての価値観を忘れ去ろうとしている。食とヒトの関りの変遷を整理すると、大きく六つの時代に分けられる。
1.原始時代
ホモ・エレクトス時代(約200万年前~30万年前)から活発な狩猟、火の使用や調理が始まった。火で調理することで食物を柔らかくし、解毒し、消化率を高めたと思われる。彼らは中型から大型の動物を活発に狩猟し、骨を割って栄養価の高い骨髄を得ていた。また、でんぷん質の地下植物を掘り起こし、火で焼いた可能性もある。季節ごとに手に入る果物、木の実、種子を採集し、幼虫、シロアリ、小型脊椎動物を餌として摂取していた。 ホモ・ハイデルベルゲンシス時代(約60万~20万年前)の食生活は、シカ、ウマ、ゾウなどの大型動物、ベリー、葉、木の実などの季節の植物、沿岸地域では貝類や魚類の利用を開始した。 ネアンデルタール時代(約40万~4万年前)の特徴は、寒冷な気候への適応、高タンパク質摂取である。マンモス、トナカイなどの肉中心の食生活であり、骨や内臓から高脂肪の栄養素を抽出していた。温暖な地域では、キノコ、ナッツ、ベリー類など、入手可能な植物性食品を採取して摂取した。また火や石器を用いて食品を加工していた。 クロマニョン時代(ヨーロッパに生息していた初期ホモ・サピエンス、約4万5000~1万年前)は、多様な雑食性、象徴的な食物利用が特徴である。多様な肉源(マンモス、アカシカ、ウマ、ノウサギ、サイガなど)と根菜、マメ科植物、野生の穀物など、幅広い食用植物を摂取していた。河川や沿岸地域では魚介類を日常的に摂取していた。また、火と基本的な発酵を利用して食品を保存・強化していた可能性が高い。さらに、食物が文化的、儀式的な意味を持つようになった(例:祝宴、埋葬の供物)。
2. 1万年前~紀元前2000年頃(狩猟採集から農耕へ) 狩猟採集時代のヒトは自ら食料を入手し消費していた。農耕への移行につれ、個人は依然として自ら食料を栽培、貯蔵、調理していたが、分業が始まり、ある者は農耕を行い、ある者は交易を行った。余剰によって専門化が進み、陶工は器を作り、製粉工は穀物を挽き、パン職人はパンを焼いた。食事のプロセスは共同体的だが、依然として個人の労働と深く結びつき、土、火などに手が触れる行為として具体化されていた。
3. 紀元前2000年頃~紀元後500年(村から都市へ) 都市が発達し、食料生産が集中化したことで、穀倉、パン屋、市場が出現した。エリート層は食事作りを召使い、奴隷、料理人に委任するようになった。公の祝宴や寺院は、食事を労働ではなく儀式として制度化した。食事は地位を示すパフォーマンスともなり、そのプロセスは外注化されたが、依然として目に見える形で残っていた。
4. 西暦1500~1800年頃(貿易と植民地拡大、ローカルからグローバルへ) 砂糖、香辛料、コーヒー等の食材が貿易によってもたらされた。保存技術(乾燥、塩漬け、発酵)によって保存期間が延長され、食べる人と産地が切り離された。専門の厨房とギルドの台頭により、個人は料理の調理からさらに遠ざかった。食事は遠く離れた場所で行われる労働の消費となり、食事のプロセスは分断された。
5. 西暦1800~1950年頃(工業化、農場から工場へ) 食品は缶詰、箱詰め、規格化といった製品へと変化した。農場は工場に、レシピはブランドに置き換えられた。都市労働者はもはや自ら栽培や調理を行わず、店で食料を購入する。プロセスは機械化され、消費者は工業生産物の受動的な受け手となった。
6. 1950年頃~現在(利便性の追求) スーパーマーケット、ファストフード、デリバリーアプリの登場により、フードサイクルはワンクリックに集約された。電子レンジ、冷凍食品、自動販売機の登場により、調理は日常生活から姿を消した。多くの人々は最終段階である「食べる」という行為のみに関与する。彼らはサプライチェーンの結節点であり、原産地、労働、そして加工とは切り離されている。ヒトにとって食事は自然との関りという意味を喪失しつつある。
食事と自然との分断と回帰
栽培、保存、流通分野の技術向上は、食事を季節や場所という軛から解放したが、一方でそれは生態系のリズムからの逸脱であり自然とのつながりを断つものでもある。さらに食の工業化の副作用として、食材の改変が生じ、その事例である栽培時の残留薬剤、遺伝子改変、保存料の添加などは食の安全性を大きく損なっている。これらはヒトと自然の調和を変調させ、健康を損なうという、食事の本来の意味を毀損する事態となっている。ヒトは自らが自然と共生する生物であることを忘れてしまい、そしてそのツケは、様々な現代病というしっぺ返しとなって現れている。
このような状況に対し、栽培、発酵、調理、消費というプロセス全体を取り戻すことが、ヒトと生態系の分断を癒す手段となる。食料を育てることは、人間を季節のリズムと地域の生物多様性と再び結びつける。小規模栽培は、土壌と腸内における微生物多様性を回復させ、生態系のフィードバックループを修復する。発酵は微生物との対話であり、ゆっくりとした生きたプロセスである。発酵は食品の保存だけでなく、文化の記憶でもあり、発酵食品一つ一つが微生物のアーカイブである。発酵食品は腸内に有益なバクテリアを再び取り込み、加工食品によって引き起こされる微生物生態系の崩壊を防ぐ。調理は、生の食材をより優れた食品へと変化させ、栄養の最適化だけでなく、文化的な表現も可能にする錬金術である。栽培から消費という食のサイクルを取り戻すことは、食事を共創へと変容させ、ヒトは自然の搾取者ではなく共生者となる。
自らが食料を栽培し調理することは、工業化された食のプロセスが奪い取ったヒトの主体性を回復する。食材は大地や海が生み出す生命であり、その入手と調理は時間と注意を捧げる儀式であり、食事は至福のひとときとなる。このプロセスは実用的と共に詩的でもあり、食べるという行為に新たな魅力を与える。自然との関係回復が求められる現代において、農事は存在の意味を回復する手段ともなりうる。
食事の目的は、生存の維持と拡大のために必要十分な栄養素を得ることである。食事で得る栄養素を基に、ヒトは活動エネルギー生成と身体の維持・成長のための素材を生産する。食物摂取が少なすぎても多すぎてもヒトの生命は危険に晒される。食料確保はヒトの進化を通じて重要事項であり、その活動は様々な文化を生み出してきた。健康であることは生存維持の必要条件であり、その根幹をなす食事は、ヒトの歴史の中で重要な関心事であり続けている。火の使用に始まる様々な調理方法の発達は、ヒトの栄養状態の改善に寄与してきた。そしてヒト社会が発展するにつれ、食事は単なる栄養摂取の範囲から逸脱し、食の美味しさに留まらず、見栄えや奇抜さが追求されるようにもなっている。
現代の食の在り様は、ヒトがその身体システムを発展させてきた数百万年から数十万年前のそれから激変している。現代社会では、自然状態の食物を摂る機会は減少しており、植物は管理された農場で栽培され、動物や魚介類も養殖により生産されているものが多い。さらに遺伝子操作により食材自体の改質も実用段階にある。また食物の加工技術の発展により、工場で食品が大量生産されるようになっている。このような人為的な食物は、保存性や味覚向上に加え利便性や経済効率性向上のために、食品添加物が使用されることが多い。そして、これらの食物の中には健康上の懸念が指摘されているものがある。食材生産や調理方法の進化に伴う食事情の変化はヒトの健康にとって、必ずしも良いことばかりではなく、悪化している部分もある。特にヒトの健康への影響が十分に把握されないまま採用されている、多様な化学物質や遺伝子組み換え操作などは要注意と言える。文明が提供する安楽な生活状態の下での現代の食事情と原始の環境に適応したヒトの身体システムとのミスマッチが、現代病と呼ばれる病態の一因とも思われる。また近年のヒトの長寿化に伴う新たな病態の顕在化もある。現代の長い生を通じて健康を維持していくことは、ヒトにとって新しい課題である。
ヒトは現代における生活環境と自らの身体システムにベストマッチする食事及び生活習慣の在り方について考察し、自分達の時代環境に適合する食形態を見極める必要がある。健康によい食事については従来から多くの研究や見解がある。ただし時代が進むと共に新しい知見が報告され、旧来の見解が覆される事態が繰返されてきた。このような経緯や人の身体システムの複雑さを勘案すると、近い将来に決定的な見解が出るとは言い難い。また、個人の体質差、生活環境の相違などを考慮すると、絶対的な健康法などは存在しないとも思われる。ヒトの健康は、暮らしている場所の環境、生活習慣からケースバイケースで、その個人に適した健康法が決まると考えるのが妥当である。そこで、過去に提案されている様々な健康食事法から、現在の情況に照らして良いと思われるものを参考に、現代以降の「健康食事仮説」を立て、それに基づき「健康食事」を追求する。
「健康食事仮説」の根本は、
1)生命システムに必要十分な栄養素を摂取する
脂質、タンパク質、炭水化物、ビタミン、ミネラル、食物繊維について必要量を摂取する
必要量は生活状況(年齢、活動、食材環境など)に応じて設定
2)生命に有害な物質の摂取を避ける(食品添加物の回避)
3)健康促進に寄与する生活習慣と並行して進める
という三原則に基づいて食事を管理することで健康を実現できる、というものである。
「健康食事」とは上記仮説に基づき開発された食事内容である。具体的には、季節に応じた食材、調理法、レシピ、食文化の開発である。食材は食材そのものに加え、入手法と入手先を含む。また、食事は美味であることを前提とする。
実行する健康食事の内容は、必ずしも健康に良いとの証明が成されている訳ではないが、個人的に良いと判断して実行するものである。そして長期に亘って健康状態の推移を調査し、仮説の検証を行う。この仮説検証は継続的に行い、適宜、検証結果を纏めることとする。