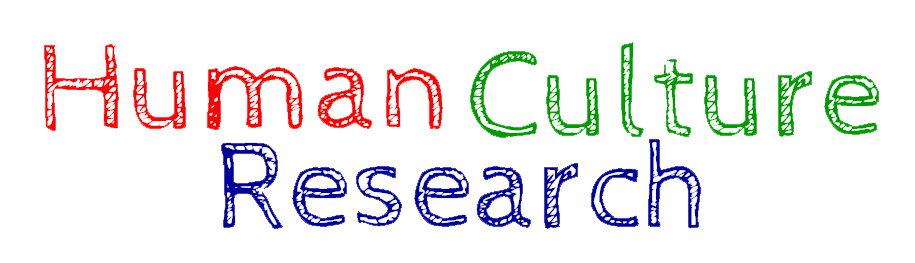キノコには、食物繊維、ビタミンD、ビタミンB群、カリウムが豊富で、特にβ-グルカン(きのこの細胞壁に多く含まれる食物繊維)が特徴です。これらの栄養素は、腸内環境を整える、カルシウムの吸収を助ける、糖質や脂質の代謝を助ける、ナトリウムの排出を促すといった効果が期待できる。特定の栄養素を含むキノコ類は、アルコールの分解や二日酔いの緩和に役立つ。
キノコに含まれる主な栄養素とその働き
食物繊維(β-グルカン)は、腸内環境を整え、便秘の改善を助ける。また血糖値の急上昇を抑え、 コレステロールの吸収を抑える働きもある。
ビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、丈夫な骨や歯の維持に役立つ。きのこはビタミンD2を豊富に含み、日光を当てることでさらに増える。
ビタミンB群(ビタミンB1、B2、ナイアシン:など)は、糖質や脂質の代謝を助け、エネルギー生成や疲労回復に有効。
カリウムは、ナトリウム(塩分)の排出を促し、血圧の調整に役立つ。 リンは、歯や骨の健康維持、エネルギー生成などに関わる。
しいたけやひらたけなどに豊富な旨味成分「グルタミン酸」は、料理の味を豊かにする。
アルコール分解に役立つキノコ類の栄養素
オルニチンは、肝臓の解毒作用を助けるアミノ酸で、アルコールの代謝に関与する。特にエリンギやマイタケ、ブナシメジなどに豊富に含まれている。
シスチン(アミノ酸)は、アルコールの代謝物「アセトアルデヒド」の解毒に必要な成分。これが豊富なキノコは、二日酔いの原因物質の分解を助ける。
ビタミンB群(特にB1とB6)は、アルコールの分解過程で消費される栄養素。キノコにはこれらが多く含まれており、エネルギー代謝や神経系のサポートにも有効。
抗酸化物質は、アルコールによる酸化ストレスを軽減する働きがあり、体の回復を助ける。また、キノコ類は水分含有量が高いため、アルコールによる脱水症状の緩和にも役立つ。一方で注意すべきキノコも存在する。ホテイシメジやヒトヨタケなど、一部のキノコはアルコールと一緒に摂取すると毒性を発揮し、激しい二日酔いや嘔吐を引き起こすことがある。これらは「酒乱キノコ」とも呼ばれ、摂取には注意が必要。
キノコ類の効率的な摂取方法
キノコは無農薬で栽培されるものが多く、その場合は、基本的には洗う必要はない(ホクトのキノコは無農薬栽培されている)。洗うと旨み成分や栄養成分(ビタミンB群などの水溶性ビタミン)が流れ出たり、水っぽくなったりする。汚れが気になる場合は、石づきを落とし、濡らしたキッチンペーパーなどで軽く拭き取る程度にする。もし洗う場合は、軽く水洗いする程度にとどめ、水っぽくならないように注意。洗った後は、キッチンペーパーで水分をしっかり拭き取ると良い。また冷凍すると細胞壁が壊れて旨み成分が出やすくなる。
カルシウムが豊富な食品(小松菜やチーズなど)と組み合わせると、ビタミンDの働きによってカルシウムの吸収がより効率的になる。またビタミンDは脂溶性のため、油と組み合わせて調理すると吸収率が上がる。
煮汁ごと食べられる汁物や煮物にすると、ビタミンB群など水溶性の栄養素が無駄なく摂れる。 きのこ入りスープや炒め物は、水分補給と栄養摂取を同時に行えるため二日酔い対策に最適。また、飲酒前のおつまみとして食べると、胃に固形物を入れることでアルコールの吸収を緩やかにし、キノコの栄養素が肝臓をサポートする。
疲労回復効果を高めるには、玉ねぎやにんにく、ネギなどアリシンを含む食材と一緒に調理するのが効果的。アリシンは、ビタミンB1と結びつくことで、より吸収されやすい「アリチアミン」という物質に変化し、アリチアミンは、体内に長く留まる性質があるため、ビタミンB1の効果を持続させ、疲労回復をサポートする。
しめじ
しめじには、ビタミンB群、ビタミンD、カリウム、そして不溶性と水溶性の食物繊維が豊富に含まれている。また、ほかのキノコよりも肝臓の働きを助けるアミノ酸の一種であるオルニチンを多く含んでおり、二日酔い予防や肝機能のサポートが期待できる。
主な栄養素と期待できる効果
ビタミンB群(ナイアシン、ビタミンB1、B2など)(三大栄養素のエネルギー代謝を助け、疲労回復を促す)
ナイアシン(アルコールの分解を助ける働きがある、二日酔い予防にも効果が期待できる)
ビタミンD(カルシウムの吸収を助け、丈夫な骨や歯を作る)
カリウム(体内の塩分を排出する働きがあり、高血圧やむくみの予防になる)
食物繊維(不溶性と水溶性の食物繊維が豊富、お腹の調子を整え、便秘解消に役立つ。糖の吸収をゆるやかにする効果があり、血糖値の急激な上昇を抑える)
オルニチン(肝臓の働きを助けるアミノ酸の一種、二日酔いの原因となる有害物質を解毒する働きをサポート)
エノキ
エノキの主な栄養素は、ビタミンB群、食物繊維、カリウムなどで、低カロリーながら栄養価が高く、特にビタミンB1が豊富。疲労回復効果があるほか、ナイアシンによる肌の健康維持、食物繊維による腸内環境を整える効果も期待できる。また、ギャバにはストレス軽減や血圧を下げる働きもある。
主な栄養素と期待できる効果
ビタミンB1(疲労回復、糖質のエネルギー代謝を助ける。きのこ類の中でも含有量がトップクラス)
ビタミンB2(脂質の代謝を促進し、皮膚や粘膜の健康維持に役立つ)
ナイアシン(エネルギー代謝を助け、肌荒れや口内炎の緩和が期待できる)
食物繊維(腸内環境を整える)
カリウム(体内の塩分を排せつし、むくみの解消を助ける)
ギャバ(脳細胞の活性化、イライラや不安を鎮める、血圧を下げる効果が期待できる)
ミネラル(マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅など)を含み、特にシイタケよりも多いとされる。 レンチナン(抗がん作用が期待される成分)
調理上の注意点
根元に培地(ばいち)が付着している場合は、それを取り除いてから調理する。また、えのきを生や半生で食べると胃腸の不調を引き起こす可能性があるため、加熱調理が必要。茶色く変色したり、ぬめりが出たりしている傷んだえのきは腐敗している可能性があるため、食べないこと。
舞茸
舞茸は、低カロリーでビタミンD、食物繊維、ビタミンB群などを豊富に含んでいる。特に注目されるのは、免疫力を高めるとされる「β-グルカン」や、カルシウムの吸収を助けるビタミンD、肌や髪の健康維持に役立つビタミンB2など。また、血中コレステロールを下げる効果も期待できる。
主な栄養素と期待される効果
β-グルカン(きのこ類の中でも豊富で、免疫力の活性化や整腸作用が期待できる。また、血圧やコレステロール値を下げる効果も期待されている)
ビタミンD(カルシウムの吸収を助け、骨の健康を維持。舞茸はキノコ類の中でもビタミンDの前駆体であるエルゴステロールの含有量がトップクラス)
ビタミンB群(B1、B2、B6など)(エネルギー代謝を助け、皮膚や粘膜の健康維持に役立つ。特にビタミンB2は、肌荒れやニキビを防ぐ効果が期待される)
食物繊維(腸内環境を整え、便通を改善する効果がある)
ミネラル(亜鉛、ナイアシン、カリウム、鉄など)(体の調子を整えるのに役立つ)
調理上の注意点
天然舞茸の場合:天然の舞茸を扱う場合は、虫や汚れがある可能性があるため、塩水に浸けて虫を出し、その後流水で洗うなどの下処理が必要です。新鮮でない舞茸は、ぬめりやカビ、異臭があるため、食べるのは避ける。また、:舞茸は生で食べるとお腹を壊すことがあるため、必ず加熱して食べる。
エリンギ
エリンギには、食物繊維、カリウム、ビタミンB群、ビタミンD、亜鉛などの栄養素が豊富。低カロリーで、エネルギー代謝や骨の健康維持に重要なビタミン類も含まれている。
主な栄養素と期待される効果
食物繊維(腸内環境を整え、便通を改善する。また満腹感を得やすく、血糖値の上昇を穏やかにする効果もある)
カリウム(体内の余分なナトリウムを排出し、高血圧の予防に役立つ)
ビタミンB群(エネルギー代謝を助ける。特にビタミンB2は、脂質の代謝に関わり、皮膚や粘膜の健康維持にも貢献する)
ビタミンD(腸管からのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける)
亜鉛(免疫機能の維持や、タンパク質の合成に関与する)
トレハロース(トレハロースは、多くのきのこ類に含まれている天然の糖類の一種。エリンギに含まれる総糖類のうち、トレハロースが94.2%を占めている。エリンギに含まれるトレハロースは、骨粗しょう症の予防に役立つ可能性が指摘されており、他の糖類と比べて糖含有量が多いものの、クセのない甘さが特徴で、ダイエットにも有効な成分として挙げられることがある)
調理上の注意点
低カロリーで満腹感を得やすいボリュームアップ食材としても適している。熱に強い:煮込みや炒め物など、加熱しても栄養素が失われにくいため、様々な調理法で楽しめる。小さく切って冷凍しておくと、いつでも手軽にスープや炒め物に使えて便利。
しいたけ
しいたけは、骨の健康を助けるビタミンD、便秘予防の食物繊維、血中コレステロールを下げるエリタデニン、エネルギー代謝を助けるビタミンB群などが豊富。低カロリーで栄養が豊富であり、免疫力向上や生活習慣病予防に役立つ。
主な栄養素と期待される効果
ビタミンD(骨や歯を丈夫にするカルシウムの吸収を助ける)
食物繊維(腸内環境を整え、便秘解消や生活習慣病予防に役立つ)
エリタデニン(悪玉コレステロールを減らし、血圧を正常に保つ働きがある)
ビタミンB群(B1、B2、B6など)(糖質や脂質の代謝を助け、エネルギー生成や疲労回復をサポートする) 葉酸(赤血球の生成を助け、貧血予防に役立つ)
グアニル酸(しいたけ特有のうま味成分で、生活習慣病予防にも有効か)
調理上の注意点
使用前に天日干しするとビタミンDの含有量を増やせる。ビタミンDは脂溶性ビタミンなので、炒め物や揚げ物など油と一緒に調理すると効率よく吸収される。汁物やスープにすると、うま味成分であるグアニル酸を無駄なく摂れる。シイタケはオーガニックで鮮度の良いものを選ぶこと。